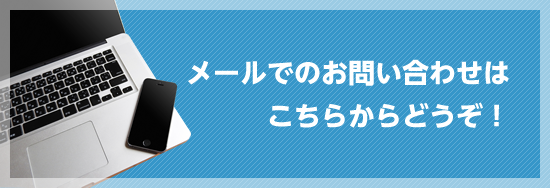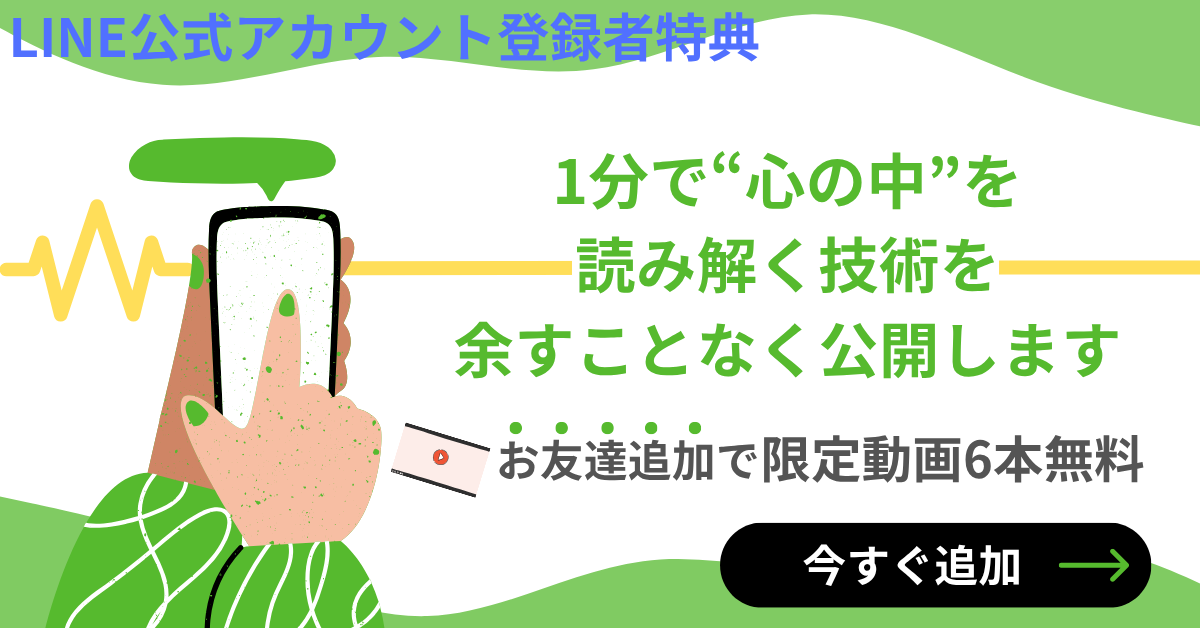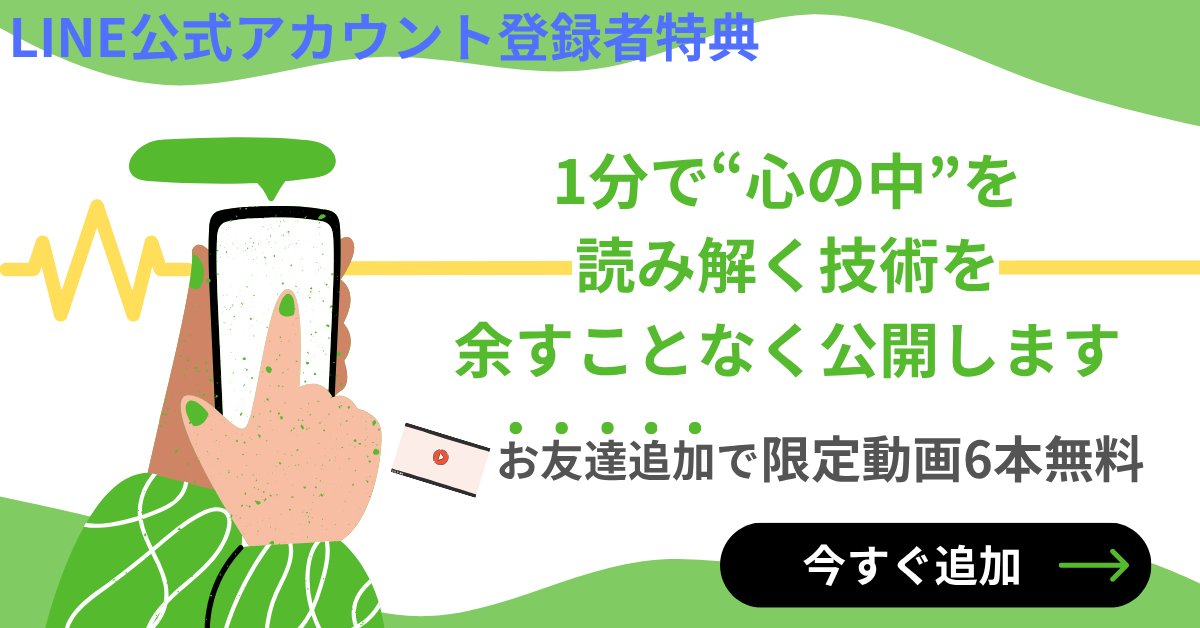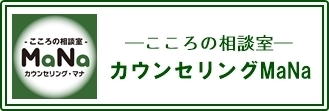身につけるNLPプラクティショナーコース

目次
- セミナーを受講してもNLPは身につかない?
- ①時間的な制約への工夫
①.1 【時間的な制約】 仕方のない実態
①.2 【時間的な制約】 私たちの工夫 - ②テクニックの網羅的な紹介スタイル
②.1 【テクニックの網羅的な紹介スタイル】 仕方のない実態
②.2 【テクニックの網羅的な紹介スタイル】 私たちの工夫 - 4.③練習するテクニックの数の多さ
③.1 【練習するテクニックの数の多さ】 仕方のない実態
③.2 【練習するテクニックの数の多さ】 私たちの工夫 - ④他者支援スキルの複雑さ
④.1 【他者支援スキルの複雑さ】 仕方のない実態
④.2 【他者支援スキルの複雑さ】 私たちの工夫 - ●NLPで他者支援するためには…
私たちClear NLP Japanの開催するNLPプラクティショナーコースは、
『自分の人生をNLPで扱えるようになる』
ことを目標地点として設定しています。
そのために『NLPが身につく』ための工夫を、コースのすべてに盛り込んでいます。
「セミナーを受講したらNLPが身につくなんて、当たり前のことじゃないか?」
そんな疑問もあるかもしれません。
「何を学ぶにしても、身につけるには本人の努力次第でしょう?」
そういう考えだってあるかもしれません。
しかし、私たち自身がNLPを学んできた過程を振り返ってみると(そしてNLPのセミナー業界を見渡してみると)、日本で一般的に開催されているNLPプラクティショナーコースは、決してNLPを身につけやすい構成にはなっていない実情があるのです。
それはおそらく、日本にNLPが輸入されてきたときから続く“仕方のない”実態のようです。
大きく次のように分けてみます。
①時間的な制約
②テクニックの網羅的な紹介スタイル
③練習するテクニックの数の多さ
④他者支援スキルの複雑さ
私たちは、これらの実態にともなう「身につけるうえでのハードル」を分析して、少しでも身につきやすくなるようにプラクティショナーコースを設計しました。
以下に、それぞれの実態と、その課題への私たちの対応とを説明します。
NLPの資格取得コースには『資格認定要件』があります。
コース中に扱う必要がある内容のことです。
プラクティショナーコースの場合、この認定要件の数が多いのです。
しかもその大部分が、NLPのテクニックの基礎とされるものです。
これら全てを紹介して、それぞれについて体験学習のための実習をすると、それだけで相当に長い時間がかかります。
ところが日本におけるプラクティショナーコースは、8日間から10日間の日程で開催されるのが一般的です。
資格認定のために求められるテクニックを一通り扱ったら、それだけで日程の大部分を占めてしまうのです。
しかも。
一般的なプラクティショナーコースでは、コーチングやカウンセリングなどの支援的コミュニケーションを練習する機会が含まれがちです。
これもまたコース全体の時間配分として大きな割合を占めます。
確かにNLPの開発された経緯が心理療法家の研究だったことを踏まえたら、支援的なコミュニケーションを扱いたくなるのも無理のないことかもしれません。
他人の悩みや目標についての相談は、NLPのテクニックを応用しやすい分野ですから。
NLPの基礎テクニックだけでも沢山あるのに、さらにコーチングやカウンセリングのトレーニングもするとなると、コースのスケジュールは相当に詰め込まれたものになるのを避けられません。
こうした時間的制約のため一般的なプラクティショナーコースでは、それぞれのテクニックを個別に一回ずつ練習して全日程を終えることになります。
復習が不足しがちな現状があるわけです。
一回で覚えるのは大変です。
繰り返すことで記憶に定着して、技術も身についていくものなのに…。
それどころか慌ただしく詰め込まれたスケジュールのせいで、効果を実感できなかったり、納得できなかったりしたら残念なことでしょう。
再受講やアシスタントをしながら習得を目指す人たちがいるのも頷ける事情です。
本コースの開催日数も他と変わりません。
ですから時間的な余裕がないのは事実といえます。
そこで私たちはコースの目標地点を
『“自分の人生”をNLPで扱えるようになる』
ところに設定することで、
実習の種類を絞り込みました。
つまり一般的なプラクティショナーコースでなされるような他者支援の技術のトレーニングをゴッソリ削除したわけです。
もちろん資格認定要件は全て含めてあります。
トレーニング内容を削除したのに資格認定要件を満たせる。
その理由は、あくまで認定要件として求められているのが「扱う内容」だからです。
それぞれの項目について、どんなトレーニングをするかは定められていません。
ですからコーチング・カウンセリングのような他者支援の形でNLPのテクニックを練習しなければいけないわけではないのです。
私たちのコースでは、これらの「コミュニケーションの技」にあたる内容も『自分のため』に応用する形で紹介しています。
自分の考えの癖を修正したり、自分の気持ちを伝わりやすい言葉にしたり、自分の課題を扱う狙いといえます。
この形であれば練習時間を大幅に削減しながら、しかも自分の人生に役立てられます。
また、講座の大部分を占める「心の癖を変えるテクニック」の実習についても、他者支援のためではない(自分に使う)手法として扱うことで作業をシンプルにしました。
NLPのテクニックは“自分の心の中を調べる”ことが特徴です。
これには慣れが求められます。
他者支援としてNLPのテクニックを学ぶと、これを他人が調べる必要が出てきます。
多くの人が最初に戸惑うこの過程を減らすことで、実習をスムーズにしているわけです。
こうして作った時間的余裕を
- NLPに求められる内省能力のトレーニング
- NLPの基礎スキルの反復
- テクニックの2段階実習(基本→簡略版)
などの体験学習に配分しています。
NLPのテクニックが自然とスムーズにできるようになり、気軽に取り組めるようになることを狙ったものです。
※他者支援を目的としたNLP、またNLPを用いたコミュニケーションについては、それぞれ特化した個別の講座を私たちは提供しています
(NLPセラピスト養成講座(準備中)、NLP2.0を参照ください)

資格認定要件として扱われるテクニックが多くなる実情と①の時間的制約とが重なって、
一般的なプラクティショナーコースでは「とにかく多くのNLPのテクニックを一通り紹介する」スタイルが主流となっています。
典型的なプラクティショナーコースは、次のような流れを繰り返しながら進みます:
- トレーナーがテクニックについて説明
- トレーナーがテクニックの手順のデモを示す
- 受講生同士でペアになって手順どおりに練習&体験
- 振り返り&質疑応答
「今から〇〇というテクニックをやります…」
「いかがだったでしょうか?では一旦、休憩です」
「さて次は△△というテクニックをやります…」
と、こんな流れで進むわけです。
このように一通りのテクニックを網羅的に紹介されれば「NLPはテクニックを集めたもの」と捉えたくなるのは仕方ありません。
数多くのテクニックが次々に紹介されて、それぞれを一度だけ体験して、
果たして「テクニックを全て覚えて使える」ようになるでしょうか?
テクニックを区別するのも大変、
覚えるのはもっと大変。
「いつ、どのテクニックを使えばいいか?」を理解して実践するのは、さらに高いハードルとなりかねません。
こうなってしまうのは「役に立つテクニックを少しでも多く教えてあげたい」というトレーナーの想いからかもしれませんが…。
受講する立場からしたら、情報量と単調な情報提供のスタイルとで、圧倒されたり混乱したりしやすいと考えられます。
テクニックをバラバラに、1つずつ紹介する。
これが関連づけた理解を難しくしてしまうのです。
こうしたバラバラな情報提供を避けるために、私たちは
(a) テクニックの原理である『心の仕組み』を説明する
(b) 『心の仕組み』そのものを日常に活かすトレーニングをする
という対応をしました。
(a)『心の仕組み』の説明
NLPプラクティショナーコースの資格認定要件には数多くのテクニックが含まれています。
これらを一様に1つひとつバラバラに紹介していくスタイルの代わりに、私たちはテクニックに重要度の重みづけをしました。
中核にあたるテクニックを重点的に扱い、実習の数も時間も増やす。
その反面、派生的な応用テクニックについては実習の比重を軽くする。
では、どのようにして中核かどうかを判断するのでしょうか?
その基準となるのが、すべてのテクニックの背後にある『心の仕組み(プログラム)』です。
NLPで考える「人間のプログラム」がどのようなものか?
プログラムによって我々がどのように動かされるのか?
プログラムの中身が変わると我々にどんな変化が起きるのか?
こうした原理をもっとも直接的に扱うテクニックを“中核”として重視します。
言い換えると、テクニックの丁寧な実習によって『心の仕組み』を体験的に理解できるようにするわけです。
そしてセミナーでは常に『心の仕組み』に立ち返って、それぞれのテクニックを関連づける説明がなされます。
色々なテクニックをバラバラに紹介する代わりに、
NLPならではの“心を扱う原理”に沿って整理して、理解を積み重ねていく形といえます。
重要な内容が繰り返されることになりますから、自然と理解が定着していくはずです。
(b)『心の仕組み』を日常に活かすトレーニング
さらにはテクニック以外にも、プログラムの観点を日常に落とし込むための実習も用意してあります。
ここには『NLPを実践する』ことを「テクニックを使う」だけに限定しない発想があります。
心の仕組みをプログラムとして捉えて、人の振る舞いを説明する。
これこそがNLPの本質で、すべてのテクニックを生み出すテクノロジーなのです。
ですから自分でも他人でも、人のすることをプログラムとして理解しようとしているときには『NLPを実践している』といえるわけです。
日常の場面で自然とプログラムの発想が浮かんでくる。そうなれたらテクニックを使っていなくても、あらゆる場面でNLPが使えることになります。
プラクティショナーコースの受講経験が自然と毎日に活かされるよう「テクノロジーとしてのNLP」をトレーニングする設計となっています。
(b)『心の仕組み』を日常に活かすトレーニング
さらにはテクニック以外にも、プログラムの観点を日常に落とし込むための実習も用意してあります。
ここには『NLPを実践する』ことを「テクニックを使う」だけに限定しない発想があります。
心の仕組みをプログラムとして捉えて、人の振る舞いを説明する。
これこそがNLPの本質で、すべてのテクニックを生み出すテクノロジーなのです。
ですから自分でも他人でも、人のすることをプログラムとして理解しようとしているときには『NLPを実践している』といえるわけです。
日常の場面で自然とプログラムの発想が浮かんでくる。
そうなれたらテクニックを使っていなくても、あらゆる場面でNLPが使えることになります。
プラクティショナーコースの受講経験が自然と毎日に活かされるよう「テクノロジーとしてのNLP」をトレーニングする設計となっています。
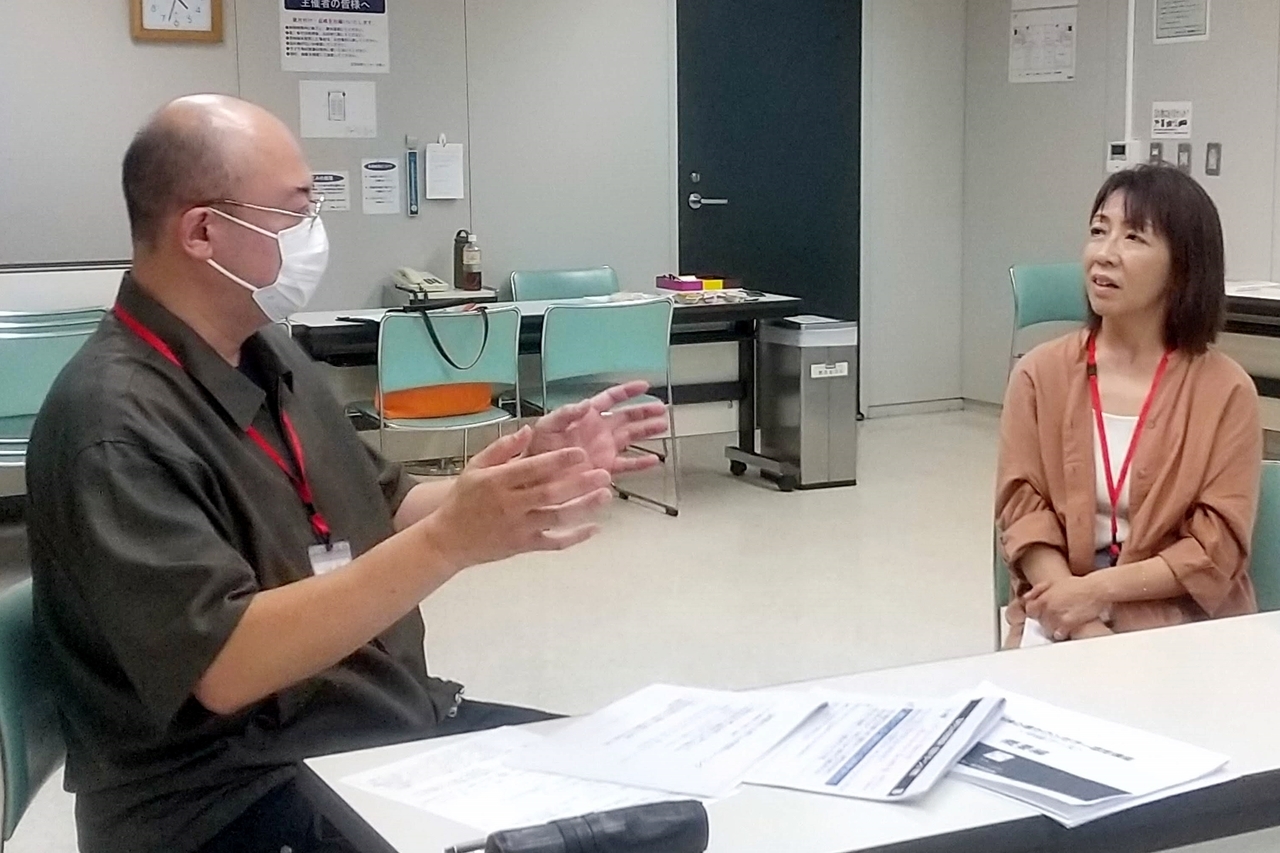
NLPが開発してきたテクニックは膨大です。
そして現在でもNLPの創始者・開発者たちは新しいテクニックを生み出し続けています。
一方でNLPの古い書籍やビデオ教材を調べれば、NLP開発初期に生み出された古典的なテクニックを見つけることもできます。
勉強熱心なトレーナーほど、自分が学んだテクニックを色々と紹介しようとするのでしょう。
どれも効果的で、それぞれ異なった用途に役立ちますから。
さらにはセミナーを開催する立場からしても、テクニックの数を増やす対応は仕方のない傾向でもあるようです。
前述のようにテクニックを網羅的に紹介するスタイルが主流の日本のNLPでは、独自性を生み出すところは「どんなテクニックを紹介するか?」になりやすいのでしょう。
プラクティショナーの資格認定要件に含まれるテクニックは、かなり共通します。
「どこでも同じテクニックが学べる」…これでは、独自性を示せません。
セミナーに個性を出して、トレーナーの強みを示す。
そのために最新のテクニックや古典テクニックを紹介するコースが多いのは納得できそうです。
しかし。
受講する立場からすると、紹介されるテクニックの数の多さが習得を難しくする側面もあります。
知っているテクニックの数が多過ぎると、
使い分けられなくなる可能性や、覚え損ねたものを使えなくなる可能性もあります。
何より数の多さに圧倒される可能性が高まります。
一度に多くを詰め込み過ぎて処理できなかったり、似たような内容に混乱してしまったり、そもそも記憶に残りにくかったり…。
扱うテクニックの数の多さは『身につける』『使う』観点からすると、厄介なものかもしれないわけです。
学ぶ段階から身につけやすく、すぐに実践できること。
そのために私たちはコース中で扱うテクニックを厳選して、数を減らしています。
あえて最新のテクニックや、古典的で有名なテクニックは含まないことにしました。
近年に開発されたNLPのテクニックは、やりやすさ・効果・実用性を高めているとはいえますが、原理は基礎テクニックと共通します。
また初期に開発されたテクニックの中に見受けられた複雑・荒削りなものは改善されて、基礎テクニックとして認定要件に含まれています。
つまり資格認定要件に含まれるテクニックで充分という判断です。
それどころか認定要件の中でも、さらに扱うボリュームを調整して、中核のテクニックを優先する構成としています。
ここには『NLPの実践』を「テクニックを使うこと」に限定しないスタンスが関係します。
人の振る舞いを『プログラム(心の仕組み)』として理解することも重視するものです。
(※私たちのコースの独自性といえる部分かもしれません)
『心の仕組み』についてのNLP特有の捉え方を踏まえると、あらゆるNLPのテクニックの背景にある原理が見えてきます。
そこで私たちはコース全体で扱うテクニックを『心の仕組み』の観点で整理して、原理的にシンプルかつ重複しにくいものを選びました。
そのため似たような印象のテクニックを扱うことがなくなり、学ぶうえで区別がしやすくなっています。
また手順がシンプルなテクニックであれば、日常でも気軽に実践しやすいはずです。
さらに私たちは、もっと手軽に使える“簡略版”のテクニックも紹介しています。
原理から考えて効果を出すのに最低限に絞った手順ですから、取り組むときのハードルも低いでしょう。
原理的にシンプルなテクニックは、心の仕組みを体験的に理解するのにも最適です。
自分の心の中がどうなっているのかを調べると、説明を聞いているだけのときとは別次元の実感が得られます。
実際にプログラムを変えたときの効果も『心の仕組み』と結びつけて納得できます。
そしてNLPのテクニックを使うときに求められるコツを身につけるのにも効果的なのです。
私たちのコースでは特に、心の中を自分で調べるときのコツを丁寧にトレーニングします。
このコツが身についているほど、NLPのテクニックの手順をスムーズに進められて、しかも効果をより大きく体感できるようになります。
コースの初日に戸惑っていた受講生が最終日には、初めてやるテクニックで大きな効果を出せるようになっている…。
その主な理由こそ「シンプルなテクニックを通してNLPのコツを身につけた」ことだろうと思われます。

プラクティショナーコースで扱われるNLPのテクニックは大きく
A. 心の癖を変える手法
B. コミュニケーションにおける技
の2つに分類できます。
A.他人の「心の癖を変える」サポート
「A. 心の癖を変える手法」は、恐怖症を消したり、感情の癖を変えたり、特定の相手との関係性を改善したり…と、用途がハッキリしています。
そしてレシピのように、手法ごとの手順も定まっているのです。
一般的には、受講生同士でペアになって、テキストに書かれた手順を見ながら実習をします。
これらの手法が効果的なのは、非日常的な体験だからこそです。
イメージを活用することで普段とは違う気づきが得られるわけです。
初めて体験する受講生にとっては馴染みのない作業です。
自分一人でテキストを見ながら進めるのは簡単ではありません。
そこでペアの形が採用されます。
一人が手順をガイドしてあげることで、もう一人が体験に専念できます。
ところが、この実習スタイルは「ガイド(支援者)-クライアント」のような構図を想定させやすくなります。
つまり
「NLPはテクニックをガイドするもの」
のように偏った印象が出やすいのです。
この発想において『NLPを実践する』こととは「NLPのテクニックで他者をサポートする」意味になりかねません。
心理療法の研究から生まれてきた背景も、他者支援の印象を強調するのでしょう。
実際のところ、他者支援を想定してNLPのテクニックを練習するコースも少なくないようです。
ガイド役の練習がメインと位置づけられるコース運営です。
クライアント役はテクニックの実習の進行をガイド役に委ねます。
だからこそガイド役に要求される技能が大きくなるのです。
心の癖を変える作業をガイド役に任せているクライアント役は、基本的に自分の世界に浸り込みます。
双方向のコミュニケーションというより、「ガイド→クライアント」の一方向性が高まる状態です。
ガイド役がクライアント役の心の癖を扱おうとするのですから、『他者の心の中を把握するスキル』が求められます(質問力、想像力、言葉の理解力、共感力など)。
そしてクライアント役の実際の体験に合わせるコミュニケーションスキルも求められます(観察力、柔軟性、安全への配慮、受け入れられやすい言葉遣いなど)。
これらが「求められるスキル」だということに注意してください。
レシピのような手順の中には含まれていない「+α」の部分なのです。
ガイド役が自ら工夫するわけです。
もちろんコース中の繰り返しによって上達していく技能ですが、これらを高めるための実習がコース中に用意されているとは限りません。
時間の制約を考えると、そのような基礎トレーニングをプラクティショナーコース中に行うのは難しいはずです。
(※私たちはコミュニケーション能力を高めるための講座を別に提供しています→参照)
初めて学ぶNLPのテクニックなのに、指定された手順以外に多くのことを求められる…。
これでは「難しい」「身につかない」「実際の場面でできる気がしない」といった印象が出ても無理はないでしょう。
B.他者への介入技術としてのコミュケーション技法
「B. コミュニケーションにおける技」とは、言語パターンや非言語メッセージの工夫のことです。
決まった使い方があるわけではなく、学習者が自ら応用するものとして用意されています。
しかしこれらも心理療法家のやり方を元にしたものですから、トレーニングのための実習にはやはり他者支援の場面が想定されやすくなる実情が見受けられます。
つまりカウンセリングやコーチングなどの相談支援を練習するわけです。
しかも使うテクニックは、そのときに紹介された言語パターンや質問法に限定して。
クライアント役の問題や目標について相談にのるということは、ある程度の“落としどころ”が求められます。
解決したり、気づきがあったり、スッキリしたり。
やりがいがあって、充実感のあるトレーニングではあるでしょう。
しかし初めてでは難しいはずです。
何よりも、相談というリアルなコミュニケーションの場を設定した実習ですから、ガイド役の受講生の多くはクライアント役のために頑張ろうとします。
練習するために用意されたテクニックを使うことより、クライアント役の話の内容のほうが重要になりがちなのです。
結果として、ただ普段どおりの自分のやり方で相談にのろうと頑張っただけ(=練習になっていない)…ということも少なくありません。
コミュニケーションの技を学ぼうとするときに、いきなり他者支援の場面を設定して練習するのは、かなり要求が高いと考えられます。
喩えるなら、野球初心者にいきなり練習試合をさせるようなものでしょう。
それでは身につくまでの道のりは遠いものとなりそうです。
ここまでにも説明してきたとおり、私たちのプラクティショナーコースは『自分の人生をNLPで扱えるようになる』ことを目標地点として設定してあります。
他者支援の側面は含めない方針です。
ですからそもそも複雑な他者支援の技術が入り込みません。
コースを通して身につけるべき内容がシンプルになっているわけです。
トレーニング課題を絞って身につけやすくする狙いです。
A.自分の心の癖を変える手順
「A. 心の癖を変える手法」については、テクニックの手順を『自分のために使う』想定で用意してあります。
ただし実習はペアが原則です。
自分で自分にテクニックを使う。
そのときのサポート役としてだけ「ガイド」がいる形です。
ガイドの役割はあくまで、テクニックを実践する本人が体験に集中しやすくするところ。
本人が手順をいちいち確認しなくても済むようにサポートするのを原則的な役目とします。
ガイド役が“クライアント役”の心の中を調べてあげるわけではありません。
だからテクニックを体験する側が、自分の体験を通して「やり方と効果」を学ぶことができます。
自分ごととして強く実感できるからこそ記憶が定着しやすく、早くNLPが身につくわけです。
自分で自分の心の中を調べて、
自分で心の中を修正する方法を試して、
自分で効果を実感する。
自分に使う流れでテクニックを練習しますから、日常的にも「自分でやる」発想が起きやすくなります。
特に重要なのが「自分の心の中を詳しく調べる」経験です。
これこそがプログラムの“中身”を理解できるNLP実践者として、もっとも役立つトレーニングとなります。
B.コミュケーションの技の基礎トレーニング
「B. コミュニケーションにおける技」については、本プラクティショナーコースでは技そのものに特化したトレーニングに留めています。
応用ではなく基礎練習ということです。
高度な技術が求められる相談を想定した応用は扱いません。
代わりに自分の心を扱うための使い方を練習します。
ネガティブな考えを修正したり、
自分の気持ちを伝わりやすくする形に整えたり、
他者との距離感を調整したり。
自分の人生に役立つ形での応用方法です。
これなら日常への実用性が高いうえに、他人を相手にしたリアルなコミュニケーションとしてのトレーニングがいらなくなります。
自分のペースでコツコツ練習できるため、身につくのが早いわけです。
野球の喩えに戻るなら、素振りやノックなどの基礎練習のような位置づけといえるでしょう。
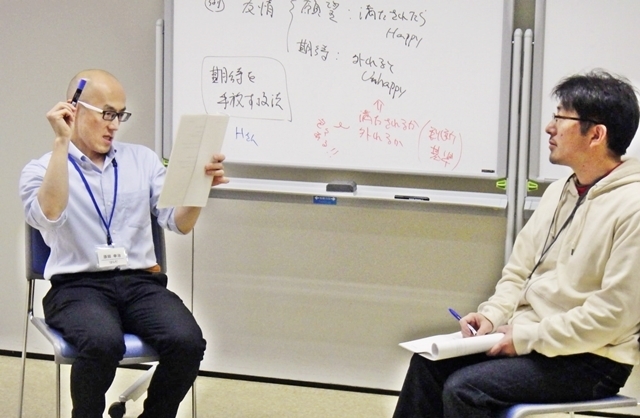
最後に強調しておきたいのは、私たちが他者支援の技術を扱わないわけではないということです。
『自分のため』を先にやる。
必要であれば『他人のため』をその後にやる。
あくまで順番の問題なのです。
もちろん大きな理由は、NLPを学びたい人の全員が他者支援を想定しているわけではないところです。
それ以上に私たちは自らの経験上、
他者支援をするにしても『自分のため』にNLPをどれだけやったかが土台になる
と知っています。
「A. 心の癖を変える手法」を他人に使うときの最重要ポイントは「どれだけ心の中を詳しく正確に扱えるか?」です。
そのためにはまず、心の中を詳しく理解する技能が求められます。
自分自身の心の中をどれだけ眺めたかによって、着眼点もイメージ力も共感力も身につきます。
この経験があるからこそ、他人の心の中を調べるときにも何を把握すれば良いかが分かり、的確なインタビューをできるようになるのです。
それともう1つ、『心の癖』を変えるためにプログラムの中身を修正する技能も重要です。
「心の中で起きていることのうち、どの部分を、どんな形に変更するか?」、つまりプログラムの中身を修正するときの方向性を見つけることも求められるわけです。
これにもやはり自分自身の心の癖を変えてきた経験が役立ちます。
自分のためにNLPのテクニックを使って、効果を実感してきた経験。
それによって「どのように心の中を変えると、どんな結果になるか?」のデータベースが作られます。
そこからプログラムの中身を修正する方針が見つかってきます。
心の仕組みは万人に共通だからです。
相手の心の中に起きていることを自分でシミュレーションしたときに、共感的な理解と、心の癖を変えるためのアイデアとが浮かぶようになるのです。
これは「過去に自分がどんな努力をしたら上手くいったか」を、他人ごとの“行動案”としてアドバイスするのとは別物です。
自分が遭遇したことのない問題でも、
相手の心の中を調べて、それを自分の心でシミュレーションしたら、相手の問題を仮想的に共有できます。
その問題への対処法を、いつも通り自分の問題を解決するときのように考えます。
どんな風に心の中を変えればいいかを自分ごとのように探るわけです。
こう考えると「自分のためにNLPを実践してきた経験の量」が、いかに重要かも分かってもらえるのではないでしょうか。
そして『自分のためのNLP』で経験を積んだ後、「他人のためにもNLPを使って支援したい」と考える方のために、私たちは別の講座を設けています。
<※NLPセラピスト養成講座(準備中)>
心の中を調べるコツや、心の癖を変えるテクニックの基礎はプラクティショナーコースで身につけている前提で、
同じテクニックを他者支援の場で使えるようにトレーニングする内容です。
質問力、想像力、言葉の理解力、共感力などを磨きながら、実践的に『他者の心の中を把握するスキル』を養います。
そしてテクニックの手順も、クライアント役に働きかける形で少し複雑化します。
ですが、自分に対して使ったことのあるテクニックと同じですから調整は難しくないでしょう。
むしろ自分が効果を実感しているテクニックだからこそ、自信をもってガイドできるはずです。
プロとして他者支援をすることまで想定して、全くNLPを知らないクライアントに対応するトレーニングもします。
初めてで戸惑っていたり遠慮したりしがちなクライアントに対して、安全かつ無理なくガイドできるようなコミュニケーションスキルを磨きます。
このとき、プラクティショナーコースで学んだ「コミュニケーションの技(質問法、言語パターン、非言語メッセージの使い方など)」が役立ちます。
一度理解したテクニックですから、今度は応用法を練習するだけの話です。
しかも心の癖を変えるテクニックの手順の中に含まれるように追加されます。
自然な形でコミュニケーションの中に取り入れてもらえるものと思います。
確かに別講座にすることで、受講費用も受講時間も増えてしまいます。
しかしプラクティショナーコースの時間的・量的な制約の中で、無理やり全てを詰め込むのは得策ではないと私たちは判断しました。
過度にトレーニング内容を詰め込んだプラクティショナーコースを設計して、それで受講生が使えるように身につかないリスク…。
それは避けたいという考えです。
プラクティショナーコースだけでNLPが身につく。
自分のためにNLPが使えるようになる。
自分の人生を思い通りにできるようになる。
そして自分に対してのNLPの実践経験を活かして、他の人もNLPで支援できるようになる。
このように順番を分けることが、結局は最短ルートになります。
そして何より私たちは、あなた自身を大切にすることを忘れて欲しくないのです。
「NLPを使って、他の人を助けてあげたい」…そんな想いのある人こそ。
“助けてあげたい人たち”の中に、あなた自身も含まれていると思うからです。

関連するページのご紹介
| NLPとは |
|---|
| コラム |
|---|
| セミナー選びのポイント |
|---|
| コラム |
|---|