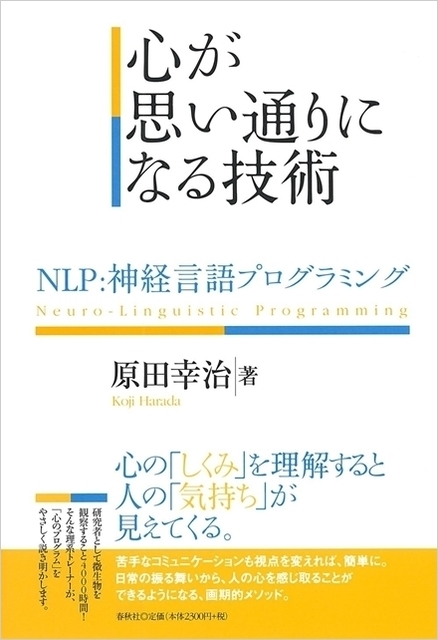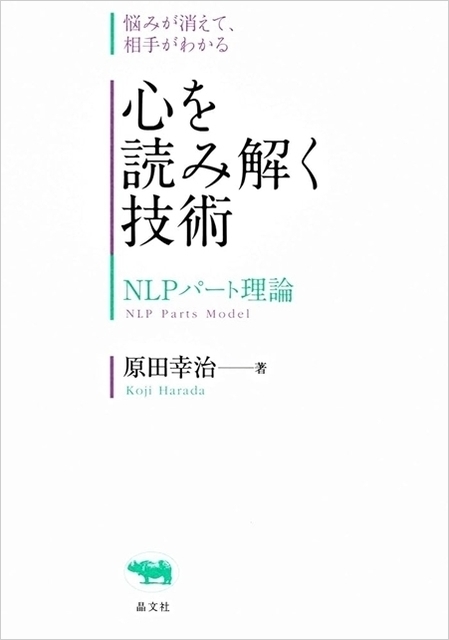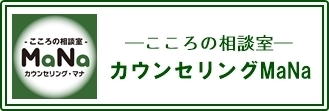コミュニケーション特化型NLP
NLP2.0
達人の叡智をあなたから…
人間関係のコツ
「あなたの人間関係がどんなものでも、
それはあなたの責任ではありません。
ただ、あなたの人間関係の原因はあなたにもあります。」
…こういうと厳しく聞こえますか?
厳しく聞こえない、
当たり前に思える、
そうだとしたら、あなたは幸運にもコミュニケーションで大事なポイントを1つ学ぶ機会に恵まれた方だといえます。
もし厳しく感じられたり、意味が分からなかったりしたとしても、心配はいりません。
私も最初はグサっときていました。
人間関係のコツの1つとして、ここで示しているのは『責任』と『原因』の区別です。
私はこれをラッキーにも、ある心理療法の達人から指導してもらえました。
当時の私は、いわゆる“お節介”で、辛そうな人を放っておけないタイプでした。
空気を読んで、人に気を遣い、揉めごとを減らそうとする感じ。
その奥に過去の経験が関係していたのは言うまでもありません。
大事な人が傷ついていても何もできなかった自分、
気持ちを押し殺して我慢してきた自分、
幼い頃の孤独な自分…。
昔の心の傷を避けるように、『人に優しくする』ことを頑張っていたのです。
だから例えば、
会社の同僚が上司から厳しく責められて、朝から夕方までデスクで突っ伏している
なんて状況を見ているのは心苦しかったものでした。
このことを相談したとき、痛烈に教わったのです。
「この問題は私の責任ではない」と。
私が悩むべき問題ではないという話です。
しかし。
もし職場や家族など、愚痴を言えたり、慰めてもらえたりする関係があったとしたら。
その同僚のストレスは軽くなっていたかもしれません。
もちろん私も、その“関係”に含まれます。
同僚と私が、そのときとは違った関係性をとれていたとしたら、状況も違っていた可能性があります。
つまり私の対応は、同僚が同じように苦しみ続けている『原因』の1つでもあったわけです。
問題の『責任』と『原因』は別のもので、それぞれに範囲があります。
- どこまでが誰の責任か?
- 何が何の原因になっているか?
これを明確にすることが
人間関係の悩みを適切に扱えるようにする重要なコツの1つだったのです。
人間関係は自分次第で変えられる!
自分に『責任』がなくても『原因』の一部になっていれば、「自分次第で変えられる」かもしれない。
この学びは私にとって、コミュニケーションに対する希望でした。
お節介をして空回りすることも、
余計なことをして相手を傷つけてしまうことも、
上手くできなくて自分が思い悩むこともなく…、
それでいて自分にできる最善を見つけられるようになりました。
どんな人間関係でも「自分次第」で変えられる余地があるのです。
大きく分けると
①自分の“心の癖”
②自分の“対応”
の2通りの方針です。
① ”心の癖”を変える
NLPの資格取得コースで得られるメリットは、主に①“心の癖”を修正できるところにあります。
感情や気持ちが動いてしまって、思い通りにコミュニケーションできないときには、厄介な“心の癖”が働いています。
それを変えるだけで激変する人間関係が数えきれないほどあります。
私たちのプラクティショナーコースは①“心の癖”を扱うことに大きな重点を置いているのが特徴です(→詳しくはこちら)。
どんな高度な技術も、自分の感情が乱されてしまったら使えません。
ですから私たちは、まず①“心の癖”を改善するほうをオススメしているのです。
② ”対応”を技術として学ぶ
しかし本音を言えば。
人間関係を良くしたいのなら②“対応”を技術として学ぶことも大切です。
①“心の癖”を修正できれば、人間関係で「大きく悩む」ことは激減します。しかしそれは、あくまで「自分が悩まなくなる」方向なのです。
気持ちが楽になることは凄く大切です。
人間関係で悩み苦しんできた人は、少しでも早く楽になっていただきたい。
ただし「悩まなくなる」のと「関係が良くなる」のは別のことです。
例えば…
- 状況は何も変わっていないけれど、上手く自分の気持ちを扱えるようになった。
- 関係は相変わらずだけど、どうしようもないことに悩まなくなった。
- 相手は変えられないから、信じて見守るしかない。
- 不快になるだけバカバカしいから、関係を切った。
さまざまな形で「悩まなくなる」ことは可能です。
しかし。
本当に『変えられない』のでしょうか?
完全に『どうしようもない』のでしょうか?
その関係性に自分が含まれている以上、変えられる可能性はゼロではありません。
少なくとも私は思い知りました。
「できることが残っているのに、やり方を知らないだけで早く諦めすぎていた…」
もちろん、どれだけ『変える』ために努力するかは人それぞれです。「どこまでやって諦めるか」に正解はありません。
大事なのは、あなたの気持ちでしょう。
『変えたい』気持ちがあるかどうか?
もし、あなたに大切な人がいて、
その人との関係で悩んでいたとしたら…
その人のために願っていることがあるとしたら…
一緒の時間を良いものにしたい気持ちが少しでもあるのなら…
「どのように関わるかという具体的な対応を工夫する」選択肢もあります。
効果的なコミュニケーション技術を身につける方針です。
私たちは教えてもらえていない
このように言うと、
「いや、もう散々コミュニケーション技術はやってきた。色々と勉強して、練習して、実際にやってみた。…でも上手くいかなかったんだ」
と思う方もいるかもしれません。
私自身がそうでした。
人間関係で悩み、NLPを始め、自分の気持ちは一気に楽になりました。
感情を揺さぶられることは多々あっても、思い悩むことはほとんどなくなりました。
それでも実際の人間関係も、身の回りの状況も何一つ変わっていない。
私は何かできないか、と働きかけ続けました。
方法を変え、相手を変え、ジタバタし続けたんです。
願ったような結果には繋がらなかったから。
そして、NLPのコースで学んだやり方では不十分だと感じた私は、コミュニケーション技術の学びの幅を広げることにしました。
コーチング、カウンセリング、催眠療法のトレーニングを受け、さらにはマジックや占い師の話術など、裏ワザみたいなテクニックまで幅広く学びました。
それぞれの技術は上手くなった実感があります。
ですが、最も肝心なはずの“自分の人間関係”は相変わらずだったのです。
なぜでしょうか?
当時の私はこんな風に結論を出していました。
「どんなコミュニケーション技術を使っても、プライベートな人間関係は難しい」
しかし、それは誤解だったと後から気づくことになります。
なぜなら私の人間関係は、あるトレーニングをきっかけに大きく改善していったからです。
コミュニケーション技術の学びを広げていた過程で、先に述べたとおり、心理療法の達人として知られている先生と巡り会えました。
その先生のトレーニングは「参加者一人ひとりに合わせて指導方法が変わる」という独特なものでした。
講義や技術トレーニングと並行して、その人に必要な学びが体験的に提供されるのです。
一部の内容はコーチングやNLPで説明がつきました。
本人に気づきを促して、自分で問題を解決するものとして。
それとは別に、もっと教育的なトレーニングもありました。
「その人が生育過程で身につけられなかった人間関係のコツ」を、考え方や態度のレベルで染み込ませるような体験学習です。
これが本当に大きかったのです。
- 「人を信頼する」とは、どういうことか?
- 「ゆるす」とは何か?
- 「尊重する」とは、どんな態度か?
- 「期待を手放す」には、どうすればいいのか?
- 「素直な気持ち」とは、どういう内容のメッセージか?
- 「操作」ではなく「相手を動かす」には何をするのか?
そして最初に出てきた
- 「何が誰の『責任』で、自分はどんな『原因』になっているか?」
も、こうした学びの一つでした。
何一つとして、私は知りませんでした。
勘違いだらけでした。
例えば…
- 「ゆるす」つもりが「我慢」していた
- 「期待を手放す」つもりで「願望も捨てていた」
- 「素直な気持ち」のつもりで「思いつくままに不満をぶちまける」ばかりだった
どうでしょう?
あなたは自信をもって、これらの問いに答えられますか?
私は少なくとも、そのときまで一度も、誰からも、こういうことを教えてもらえていませんでした。
単純に知りませんでした。
ここがポイントです。
『知らない』のです。
こんなに大事なことを、なぜ私は『知らなかった』のでしょうか?
答えはカンタンです。
『ほとんど教えられていないから』
それでは、なぜ教えられることがないのか?
こんなにもコミュニケーション技術のセミナーや本が沢山あるのに、です。
そこには日本で“コミュニケーション技術”が紹介されるときの宿命ともいえる盲点があります。
ここに目を向けていただきたいのです。
コミュニケーションの学びの盲点
日本で「コミュニケーション」を学ぶ機会を大きく分けると、
- コミュニケーション能力を高める研修
- コーチングやカウンセリングなどの専門技術トレーニング
- 営業、子育て、話し方、マナーなどのノウハウの講座
のどれかに当てはめられそうです。
それぞれの方が「これをやったら自分の人間関係の困りごとが解決しそうだ」と期待をして参加します。
その内容が自分に必要なものとピッタリ合っていればいいのですが…。
そうならないことが多いのは、次のような盲点があるからです。
【盲点①】コミュニケーションの分野
- 人間関係で望ましいとされる対応は場面ごとに異なる
(例:「相談に乗る」vs.「気持ちを伝える」vs.「仲良くなる」etc.) - 「コミュニケーション技術」という呼び方は「スポーツ技術」と呼ぶぐらい曖昧
- 学んでいない場面の対応は難しくて当然
《詳しいポイント解説》
世間では「コミュニケーション技術」や「コミュニケーション能力」といった、1つのスキルがあるかのように語られます。
しかし人間関係には様々な『場面』があります。
場面ごとに求められる『対応方法』も沢山あります。
例えば「悩み相談にのる」という『場面』では、望ましい『対応方法』として、
- 話を聴く
- 寄り添いの言葉をかける
- 困りごとを整理する
- 解決の方針を話し合う
などがありそうです。
これが「採用面接を受ける」という『場面』になると、求められる『対応方法』は例えば
- 質問の意図を理解する
- 自信をもって意見を述べる
- 分かりやすく説明する
などでしょうか。
もちろん「合コンで盛り上げる」とか、「販売員として接客する」とか、「結婚式でお祝いのスピーチをする」とか、あらゆる『場面』で求められる『対応方法』が違うわけです。
スポーツに喩えるなら『競技』ごとに求められる『技能』が違うようなもの。
サッカーが上手いからといって、ゴルフや水泳も上手いとは限りません。種目が別物なら、求められる『技能』が違うからです。
上手くなりたかったら、それぞれの競技の教室に通うものでしょう。“スポーツ技術スクール”なんて曖昧なものはありません。
同じように“コミュニケーション技術”というのも曖昧すぎるのです。
スポーツを『競技』ごとに学ぶように、コミュニケーションも『場面』ごとのやり方として学ぶ必要があります。
当たり前の話だと思いますが、ここが意外と見過ごされているようです。
だから私も勘違いしてしまったのでしょう。
「カウンセリングとかコーチングとか、どんなコミュニケーション技術を使っても、プライベートな人間関係は難しい」と。
そうではありませんでした。
「カウンセリングやコーチングは、プライベートな人間関係とは別の場面」なのです。
カウンセリングもコーチングも“相談”という限定された場面の技術です。
プライベートな人間関係では“相談“以外のことが数えきれないほどあります。
- パートナーと話し合う
- 反抗期の子供と関わる
- 部下を指導する
- クレームに対応する
- 生徒のヤル気を高める…。
全て別の場面ですから、別の対応技術が求められるのです。
仮に、プロレベルまでコーチングを学んだのに親との関係が上手くいかなったとしても、それは当然なのです。
親との関係はコーチングではないから。
「こんなにサッカーが上手くなったのに、まったく泳げない!」と言うような話ではないでしょうか。
《原因①の要点》
ごく一部の場面に限定された対応技術しか紹介されていない
【盲点②】ゴール設定
(A)専門技術を扱う場合
- 高度にトレーニングできるが、汎用性は低い(日常の場面は少ない)
- 高度な技術習得をゴールにすると、トレーニング期間が長くなる
(B)基礎となる能力を扱う場合
- 汎用性は高いが、目標到達点は一般レベル
- 一般的にも対処が難しい場面は対象外
《詳しいポイント解説》
セミナーでも本でも動画教材でも、何かを教えるときには必ず『ゴール設定』があります。
「これをやったら、どうなれるか?」という到達点の想定です。
サッカーとかピアノの教室では、生徒の経験や技能に応じて指導内容が異なります。
それはコミュニケーションの学びでも同じです。
人間関係では本来、場面によって求められる技術が異なるわけですから、
「全ての場面で上手く対応できるようになる!」
というゴール設定は現実的ではありません。
そこで次のような選択肢がでてきます。
(A) 1つの場面に特化した技術を扱う
(B) あらゆる場面に共通する基礎を扱う
(A)1つの場面に特化した技術とは、例えばカウンセリング・コーチングなどの技法や、営業・子育て・話し方・マナーなどのノウハウが当てはまります。
学んだときの到達点(ゴール設定)としては、想定する参加者や学びの所要時間によって自由に変更できるのが特徴です。
マナー教室を例にとると、
「新社会人向けの3時間の社員研修」と
「航空会社の客室乗務員のための3ヶ月の接遇トレーニング」とで、どれだけのマナーが身につくのかは異なるはずです。
場面を特化させて時間をかければ、その分野での高度な技術を身につけやすいわけです。
しかしその反面、他の分野の技術を学べない事情は無視できないでしょう。
家族関係の改善を期待してマナー教室に行く人は少ないと思いますが、カウンセリングやコーチングを学ぶ人は見受けられます。
カウンセリング・コーチングに含まれる一部のテクニックは役立つ場面もあるかもしれませんが…。
私は一方で、
「夫と話し合いをしようとしても、コーチングをされてしまって話にならない。もっと自分事として話をして欲しいのに。」
という相談も受けたことがあります。
技術の専門性が高いときほど、「自分が求めているコミュニケーションの分野と合っているか?」には注意したいところです。
(B) あらゆる場面に共通する基礎となる内容は、社員研修やビジネススクール、短時間のセミナーなどで扱われがちです。
特定の人間関係や場面を改善しようというよりも、
- 「コミュニケーションのトラブルは避けたい」
- 「人間関係の苦手意識をなくしたい」
- 「人づきあいの基礎ぐらいは知っておきたい」
といった目的に合わせたゴール設定です。
そのため
- 話を聴く
- 質問する
- 分かりやすく伝える
- 気持ちを汲みとる
- 会話のバランスをとる
など、
コミュニケーションで頻繁に用いる『作業』を満遍なく練習する傾向があります。
スポーツに喩えると、
ランニングしたり、ストレッチしたり、筋トレしたり…といった、基礎能力のトレーニングのようなものです。
ですから、コミュニケーション“技術”ではなく、コミュニケーション“能力”を扱うケースといえます。
どんな場面でも役立つ有効な学びである反面、トレーニング期間が短めとなることもあって、到達点は「無難に人間関係をこなす」あたりに留まります。
一般的に多くの人が困ってしまう人間関係については、そもそも想定されていないはずです。
このように、
日常で誰もが「厄介だ」「難しい」「どうしたらいいんだろう?」と思ってしまう場面については、(A), (B)いずれのケースでも想定外というのが現状です。
本当に助けを求めている大変な人間関係こそ、多くのセミナーや教材の内容では対応できないという話です。
もし、あなたの人間関係で「これだけを何とかしたい!」というピンポイントの悩みがあるとしたら、できる限り特化した内容を学ぶのをオススメします。
例えば、
「クレーム対応セミナー」よりも「悪質クレーマーとの関わり方セミナー」、
「子育て講演会」よりも「不登校サポート講演会」、といった選び方です。
《原因②の要点》
厄介なコミュニケーションを想定した技術トレーニングがない
(※エキスパートへの個別相談がメイン)
【盲点③】文化の違い
- 人間関係の望ましい対応は文化ごとに異なる
- コミュニケーションの専門技術は、ほとんどがアメリカ由来
- 大事なのは表面的な対応よりも『人間関係の原則』
《詳しいポイント解説》
「コミュニケーション」という言葉自体が外来語であるように、「どのようにコミュニケーションするか」という『技術』も大部分がアメリカ由来です。
人間関係で望ましいとされる対応は、文化の影響を強く受けます。
例えばアメリカでは一般に「自分の意見をハッキリと述べて、他者との意見の違いを尊重しあう」といった傾向が指摘されます。相手を“独自の存在”として尊重する姿勢です。
この文化背景があるからこそ、いわゆる傾聴で“オウム返し”をするのも効果的なのです。
「それがあなたの考えなんですね」と独自性を『尊重』したメッセージに受けとってもらえます。
ところが日本文化ではもっと賛同が求められます。
「分かる!」とか「ですよねー」とか、自分の気持ちに同意してもらうことが『受容』のメッセージとされるのが文化です。
こうした文化の違いがあると、同じ“オウム返し”という技術を使ったときにも、その効果や意味合いが変わってきてしまう可能性があるわけです。
文化は幼少期から、当然のこととして染み込んでいくものです。
例えばアメリカでは、子どもを親とは別の一個人として尊重する姿勢が常に示されます。小さい頃から自立を促すコミュニケーションが一般的だということです。
しかし、その背後に「ストレートに愛情を表現する文化がある」ことを忘れてはいけません。
愛情表現によって親密さが保たれているからこそ、自立を促す形で個人としての距離をとっていても、暖かい関係性のバランスがとれているわけです。
文化は当たり前のこととして共有されるものです。
皆が当然のようにやっているから、わざわざ誰も「ストレートに愛情を伝えるのが大切です」なんて教えません。
結果としてアメリカから輸入されてくる親子のコミュニケーションの技術は、「どうしたら自立してくれるのか?」の関わり方に偏ることになります。
アメリカでは皆がやっている愛情表現のところは、技術の内容には含まれにくい実情があるのです。
アメリカ人のようにストレートな愛情表現をする日本の親は少ないでしょう。
そんな人が急に、自立を促すコミュニケーションの部分だけを取り入れたとたら…?
親子の距離感が少し心配になります。
このように文化背景は、あまりに当然のこと過ぎて技術のポイントには含まれないのです。
仕方ありません。
アメリカでコミュニケーション技術を開発した人たちは、アメリカ人を対象として想定していたのですから。
それを日本人がアメリカから輸入しただけのことです。
「アメリカで最先端のやり方なんだから素晴らしいに違いない」と。
このときに文化と言語の壁が立ちはだかってしまったのでしょう。
とはいえ「文化が違うから、日本では通用しない」という話ではありません。
技術を表面的な『やり方』としてコピーしてしまうのが危険なのであって、表面的な『やり方』を生み出す土台を学ぶことは可能です。
文化を超えて人間関係に共通する土台の考え方が『人間関係の原則』です。
同じ原則が、別の文化背景では、表面的には別の技術に落とし込まれるわけです。
例えば人間であれば、誰でも自分のことを認めてもらいたいものです。そこから「相手を承認する」という原則が出てきます。
この「承認」がアメリカでは「独自性の尊重」として、日本では「賛同による一体感」として表現される、と。
だからこそ、文化背景の違いを踏まえながら『人間関係の原則』のほうを身につけるのが効果的なのです。
ただ現状では残念ながら、表面的な対応技術のみが直輸入されがちなようで…。
大事な原則が抜け落ちてしまっている可能性に注意したいところです。
《原因③の要点》
文化背景の違いを踏まえずに輸入した技術からは、重要な『人間関係の原則』が抜けてしまう
【まとめ:「コミュニケーション技術」の学びの盲点】
①コミュニケーションの分野
『ごく一部の場面に限定された対応技術しか紹介されていない』
②ゴール設定
厄介なコミュニケーションを想定した技術トレーニングがない
③文化の違い
文化背景の違いを踏まえずに輸入した技術からは、
より本質的な『人間関係の原則』が抜けてしまう
方法はある
ここまで見てきたように、日本で紹介されている「コミュニケーション技術」には、
- 親密な関係での対応方法が含まれない
(分野の問題) - 厄介なケースの対応方法が含まれない
(設定レベルの問題) - 日本に合った対応方法が含まれない
(文化差の問題)
という特徴があります。
しかしながら私が運よく学べたように、日本における親密な人間関係で起きがちな厄介なコミュニケーションを改善する方法は存在しています。
そのカギこそが『人間関係の原則』を身につけるところにあるのです。
これを日本文化に合わせながら、人間関係のそれぞれの場面に応用すれば、表面的なテクニックでは対処できなかった厄介なコミュニケーションも適切にこなせるようになります。
実のところ、この作業を自ら完了させたのが、私を指導してくれた先生でした。
先生のバッグラウンドには家族療法のトレーニングがあります。
家族療法とは「夫婦や家族関係の問題解決を援助する心理療法」ですが、その中に『人間関係の原則』を体験的に指導する流派があるのです。
まさに私自身も、この家族療法を元にした指導をしてもらっていました。
日本でも家族療法を提供しているところはありますから、同様の指導を個別で受けに行くこともできるでしょう。
とはいえ家族療法としてカウンセリングを受けるときには、目下の具体的な問題を解決することに焦点が当たるものです。
“一生もの”の人間関係の技術を学びに行くところではありません。
いつまでも人間関係は着いてまわります。
未来にも新たな出会いが続いていきます。
同じ相手でも時期が変われば、求められる関係性が変わります。
私たちに求められる人間関係の対応は、常に変わり続けていくのです。
この先の毎日がどんな様子になるか…?
それを大きく左右するのが人間関係ではないでしょうか。
もし、あなたが「目下の人間関係の悩みを解決したい!」と強く願っているなら、専門家に相談するのもオススメです。
もし、あなたが「自分のコミュニケーションを変えて状況を改善したい」と思ったことがあったとしたら、『人間関係の原則』を知ってみるのも1つでしょう。
正直に言うと…
昔の自分に一番教えてあげたい内容
そうはいっても、です。
『人間関係の原則』はあくまで原則であって、具体的な対応技術ではありません。
繰り返しになりますが、効果的なコミュニケーションの技術とは「文化に合わせた場面ごとの対応法」です。
原則を日本文化に合わせた形で、場面ごとに応用していく必要があります。
残念ながら、この作業に労力が求められてしまうことは否定できません。
そこでオススメなのが、
「『人間関係の原則』に沿って、人間関係を見事にこなしている“身近な達人”を手本にする」
ことです。
原則を理解していれば、その通りにやっている人を見たときに気づくことができます。
「なるほど。この場面だと、こんな対応にする手があるか!」と。
「いや、そんなに暇じゃない」
「色々な場面で、それぞれ達人なんか見つけられるの?」
「もっと効率的に技術を知りたい」
…そんな方は、次の選択肢も検討してみてください。
私が見つけた“身近な達人”の対応法を、場面ごとのコミュニケーション技術として整理したトレーニングプログラム
です。
かなりの部分で、私に指導してくれた心理療法の達人のやり方が参考にされています。
ですが先生だって、全ての分野で万能なわけではありません。
そこで私が運良く知り合えた達人たちもお手本とさせてもらいました。
- 売り上げNo. 1のセールスマン
- ヒット作を連発する敏腕編集者
- 職場の魔法使いと呼ばれたケアマネージャー
- クレーマーをリピーターに変えるお客様相談係
- 多文化・多国籍の学生を協調させる大学教授
- チェーン店のレストランなのにファンが集まるホールスタッフ…。
『人間関係の原則』を見事に現場で使っているところを見たときには感動したものです。
こうした達人たちのコミュニケーションのやり方を、技術として習得しやすくなるように、NLPの観点でポイントを整理しました。
場面は多岐にわたりますが、私のトレーナー経験を踏まえて、あえて12に厳選しています。多くの参加者から聞いた人間関係の悩みや問題をもとに、皆さんに共通して役立ちそうな場面を選びました。
想定した場面ごとに、技術のポイントを心がけつつ、実際のコミュニケーションの形でトレーニングをするプログラムとなっています。
場面ごとの技術を習得する趣旨だけでなく、根底に含まれる『人間関係の原則』を繰り返しの体験で身につけやすいようにデザインされています。
正直に言うと…
昔の私に一番教えてあげたい内容です。NLPをはじめとして、色々なセミナーに参加しまくっていた頃の自分に。
でもまあ、仕方ないでしょう。
それは誰でも同じだと思います。
NLPを学んだ方も「もっと早く知りたかった」と口を揃えますから。
トレーナー紹介
トレーナーは、Clear NLP Japanの原田幸治です。

原田 幸治
- 米国NLP™協会NLP™トレーナー
- コミュニケーション・コンサルタント
- HRD Lab代表
- パラゲート・サンガ主催
早稲田大学大学院理工学研究科修了後、バイオ系企業において研究者として勤務したのち、2007年にNLPトレーナーとして独立。
200回以上の資格取得コースを担当し、約3000人の受講生と関わってきた。
スーパーバイズのクライアントは、カウンセラー、福祉相談員、医療従事者、研修講師、大学教授、経営者、会社員と多岐にわたる。
NLPとの出会いは研究職時代。
ストレスや人間関係の悩みからコミュニケーション技術や心理について学び始め、NLPの資格取得コースを受講する。
人とリアルに触れ合い、心と深く向き合う喜びから、トレーナーとしてNLPを伝える道を選ぶことに。
講座や個人セッションを通して多くの人生の転機と関わる重みを知るほどに、自らの研鑽の重要性を思い知らされ、学びと実践を続けながら今に至る。
生命科学の研究者として培った分析的視点と、心理臨床家から受けたトレーニングを基にした、NLP特有の『心の仕組み』の観点で人の心理を紐解くスタイルを基本とする。
NLPに対するスタンスは、トレーナーというよりもプラクティショナー(実践者)。
NLPの技法は合計で数千回、自分の問題に対して実践してきた。
実践経験に基づいて「本格的な内容を分かりやすく」説明することを心がけている。
著者に『心が思い通りになる技術:NLP:神経言語プログラミング』(春秋社)、『心を読み解く技術:NLPパート理論』(晶文社)がある。
セミナーの特徴
- 多くの人が遭遇する人間関係
- 「無難な関係」から「親密な関係」まで
- 「そつなくこなす」から「厄介な問題の解決」まで
- 2人間関係の原理を体験的に
- ×「伝える&受けとる技術」よりも、○「分かり合う技術」
- 『人間関係の原則』が含まれた実習
- 繰り返しで自然と身につく(暗記不要)
- 3日本の達人のやり方
- 知らないとできない効果的な技術
- 日本で実際になされていた自然なやり方を参考に
- 効果は達人の成果で確認ずみ
- 4NLP的なモデリングで習得
- 技術のコツをNLPの着眼点で網羅
- NLP用語による説明だから誤解が少ない
- NLPの経験があるほど習得がスムーズ
- 5自分のペースで無理なく上達
- 実習以外にも解説とデモを動画でいつでも学べる
- 人間関係の技術を学ぶ最重要ポイント『見る』を好きなだけ
- 自分にとって大事な技術へ集中的に取り組むことも可能
詳しいポイント解説はこちら
上にも述べたように、人間関係で求められる対応は場面ごとに異なります。そこで場面ごとに特化した形で技術を身につけるスタイルを採用しました。
選んだ場面は、多くの人が遭遇しやすいもの、そして多くの人にとって厄介なものです。
無難に乗り切るのが期待される雑談や社交から、相手の気持ちを深く聞き出す場面、ネガティブな感情がぶつかり合う場面まで、幅広く学びます。
世間一般のコミュニケーションセミナーでは扱われない複雑な人間関係も対象とするのが大きな特徴です。
その意味では、いわゆる“入門レベル”ではないかもしれません。
例えば
- 「人見知りが酷く、いつも何も言えなくなってしまいます」
- 「人間が怖くて、人と関わるのを避けてきました」
- 「話しかけられても何を答えたらいいか分からなくて困ってしまいます」
といった場合には、別のセミナーから始めたほうがスムーズかもしれません。
特に、人づきあいへの苦手意識については、対応技術の問題というよりも、過去の心の傷が影響している可能性もあり得ます。
つまり“心の癖”です。
その場合には、NLPプラクティショナーコースの受講のほうが適しているとも考えられます。
ご自身の状況について心配なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
また、特定のコミュニケーション形式を扱うわけではないところにもご注意ください。
例えば、カウンセリングやコーチング、プレゼンテーション、採用面接、セールストーク、接客などのように、専門家のための技術トレーニングではありません。
もう少し一般化された対応技術となります。
例えば、
- 「相談」
- 「説得力のある伝え方」
- 「相手の考えやニーズを聞き出す」
- 「好感を持ってもらう」
のような形です。
詳しい内容は以下の『身につける技術』のところをご覧ください。
シンプルに言うと、コミュニケーションとは「考えや感情を伝達する」ことです。その伝達手段として、言語メッセージと非言語メッセージとがあります。
そのため「伝わるかどうか」に焦点が当たります。
「どんなメッセージなら相手に伝わりやすいか?」
「どうやって相手のメッセージを受けとるか?」
ここには『伝ったあとの結果』が含まれていません。
極端なことをいえば、
「はい、伝わりました。よく理解できました。でも私には関係ありません。無視します。」
といったケースもあり得るわけです。
しかし私たちは勝手に
「ちゃんと伝わったら、自分の望む結果になるのだろう」
と想像してしまいがちです。
そんなことはありません。
相手には相手の気持ちがあります。
ですから大事なのは「伝わるかどうか」だけではなく、「分かり合えるかどうか」なのです。
ただ「へー、そうなんだー」と知るだけでは不十分。
「ああ、そうか…。それなら、そうだよなぁ」と、感情や価値観のレベルで納得するところまで求められます。
つまり「お互いの気持ちが動く」ことが想定されているはずなのです。
もちろん、納得し合えたからといって、必ずしも望んだ結果になるとは限りません。どうにもならない事情や、個人の自由がありますから。
それでも、です。
お互いに納得し合えたときには、少なくとも「分かり合えた」という実感は得られます。
ここが『人間関係の技術』のゴールではないでしょうか?
私たちには残念ながら、この『人間関係の技術』を学ぶ機会が滅多にないのです。
「伝える&受けとる」という“コミュニケーション”に焦点が当たって、「分かり合える」という『人間関係』が見過ごされがちです。
人間関係を良くしていくには、「伝える&受けとる」を超えた、『分かり合う』工夫が必要なのです。
そのために『人間関係の原則』を知っていることが役立ちます。
例えば「腹を割って話し合えば、いつか分かり合える」という意見があります。可能性はゼロではありませんが、決して高くはありません。
なぜなら
『人は自分の本心を言葉にできない』
からです。
本心として含むべき情報を知らなければ、本心を自覚することも、それを適切な言葉に置き換えることも当然ながらできません。
だからこそ原則を知って、原則に基づいた対応を工夫する必要があるわけです。
このトレーニングプログラムでは『人間関係の原則』が自然と体験的に身につきやすいように、実習内容をデザインしてあります。
場面ごとの技術の中に、共通して何度も『人間関係の原則』が登場しますから、暗記の必要なく身につけられるはずです。
当たり前の話ですが、技術を身につける上で最も欠かせないのは『知っている』ことです。
私たちは母国語を自然に身につけてきただけでなく、場面ごとの対応方法までも経験を通じて自然と身につけてきています。
例えば、友達づきあいは同級生との関わりを通して身につけます。
上司としての振る舞いは、自分の上司を参考にするでしょう。
子供への関わり方も、自分の親が基準になります。
若者の間で流行が起きたり、親にされて嫌だったことの反対をやったり、いくらかのアレンジはあり得ます。
しかしながら、そこには必ず「元になるもの」があります。私たちが全く新しいことを作り出すことは滅多にありません。
私たちのコミュニケーションのやり方は、誰かを見本として参考にしながら身につけたものだということです。
さまざまなハラスメントが問題とされながら一向に解決しないのも、ここに原因があると言えます。
「これをしてはダメです」と言われても、誰も代わりの『適切な対応方法』を知らないのです。
どうしていいか分からない。
それどころかむしろ、ダメだと言われても癖になってしまった対応が自然と出てしまうのを止められない人も多いことでしょう。
人間関係において対応方法を変えるには、別の方法を『見て、知って』、参考にする必要があるわけです。
上手くいかない状況を改善したいのであれば、なおさら効果的な対応方法の見本が大事になります。
だからこそ本トレーニングプログラムでは、さまざまな場面における人間関係の達人を見本として、技術の形に落とし込みました。
具体的で、しかも現場で実際に効果を発揮していた対応を参考にしています。日本で見つけた達人たちですから、日本文化に合っている方法であることは言うまでもありません。
“上手くいくやり方”から「コツ」や「型」を取り出すことを広く『モデリング』と呼びますが、モデリングの流儀は人それぞれです。
この流儀の個人差によって、技術の学びやすさが異なります。個人差は大きく分けると、次の2つで表れます。
1つは着眼点。
技術のポイントとして何を取り上げるか?です。
モデリングした本人にとって「ここを心がけると上手くいく」というポイントが選び出されます。
しかしながら学習者にとっても、そのポイントが同じように重要とは限りません。
逆に本人にとって当たり前にやっていることは、わざわざポイントとして取り上げられることもないでしょう。
他の人には重要かもしれなくても、です。
もう1つ個人差が表れやすいのは、説明の用語です。
本人がどんな言葉でポイントを伝えるか?です。
技術のポイントとなるのは、主観的に「何をやっているか?」という体験の中身です。
これを言葉に置き換えようとすると、その人ならではの言い回しになってしまうのが避けられません。
そうした言葉の表現が、学習者にも同じように伝わるとは限りません。言葉のレベルで理解できないこともあり得るわけです。
これら2つの個人差の要因、❶着眼点と❷説明の用語があるからこそ、学習者との相性が出てきてしまうといえます。
同じ人から指導を受けても上達度合いに差が出るのは、単純に“才能”の一言で片付けられないものがあるのです。
その点、本トレーニングプログラムに含まれる技術は、すべてNLPの流儀で達人をモデリングしたものです。
NLPは『主観的体験の構造の研究』と定義されるように、誰かの主観的な体験内容を調べるのが専門です。
主観的な体験内容のうち、どの部分に着目するかが決まっているのです。
人間に共通する『体験の構造』があると考えて、「その構造のどこに、どんな特徴があるか?」で個人差を調べます。
喩えるなら、家の設計図のようなものです。
家の構造には大まかな共通点がありますが、どこかの長さ・大きさや建築材料が変われば、完成する家は別物になります。ただしインテリアや家具は、家の本質ではありません。
同じようにNLPでモデリングするときには、調べるべき要素が決まっているわけです。
だからこそ、本質的な特徴を逃すことなく、かといって複雑になり過ぎず、シンプルで効果的な技術を抽出できるのです。
一般的なモデリングよりも効果的に、万人向けの技術を作り出すことができるといえます。
しかもNLPでモデリングをする以上、その説明の用語はすべてNLP用語になります。
説明スタイルに一貫性があって、用語が明確に定義されていますから、誤解も起きにくいことになります。
とりわけ一度NLPを学んだ経験のある方であれば、用語に馴染みがあるだけでなく、NLP的な体験学習のスタイルにも慣れていますから、よりいっそう効率的に身につけられると期待されます。
場面ごとの対応技術は、全部で12あります。
一部には人間関係の土台となる基礎トレーニングも含まれますが、大部分は独立した別の技術と考えていただいて構いません。
つまり「全部を網羅しなくても大丈夫」ということです。
自分にとって重要度や関連性が高い技術を選んで、集中的に取り組むことも可能です。
(※実際には『人間関係の原則』が繰り返し表れるため、一通りトレーニングすると効果が上がると考えられます)
また1つの技術を身につけるためにも、覚える必要がある知識は決して多くありません。ポイントや手順は定式化してありますが、暗記するものでもありません。
むしろ理解をしたうえで、実際のやり方を『体験的に学ぶ』のが効果的です。
そこで本トレーニングプログラムでは、さまざまな形で技術を“体験”できるように設計してあります。
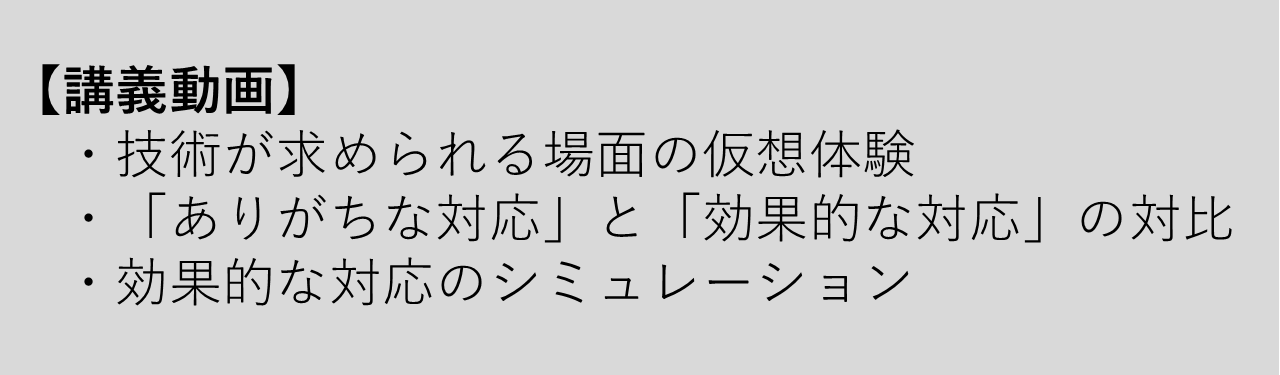
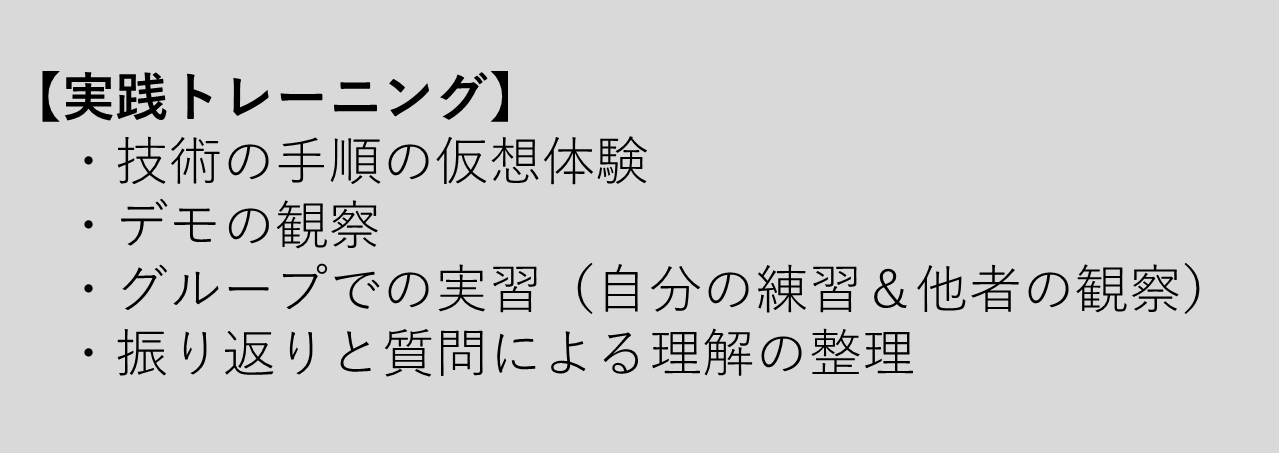
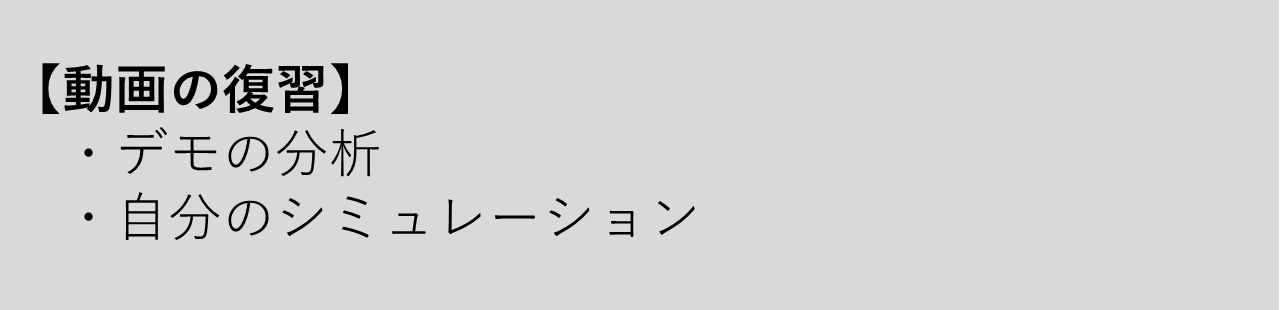
“体験”といっても、例えば小学校の体育でサッカーをやるときのように「とりあえずやってみる」という種類のものではありません。
世間には“体験型セミナー”が数多くありますが、その多くは
「とりあえずやってみる」→「振り返って気づきを得る」
という『気づき重視スタイル』のようです。
限られた時間のセミナーで学びを得てもらって、満足度を高めるためには有効な方針です。
しかしこのスタイルは『技術トレーニング』とは別物です。技術を身につけるには「コツを体感して記憶に定着させる」必要があります。
それには、技術が実際に使われている『具体的な例』が多いほど望ましく、また、コツとなるポイントを自分で捉えるための『整理』の機会も役立ちます。
デモや実習の様子を動画で何度も確認できるのは、その点で大きなメリットとなります。
特に重要なのが「見る」という体験です。
ここまでにも説明してきたとおり、私たちがコミュニケーションのやり方を自然と身につけるのは、他の人のやり方を「見る」経験を通じてです。
何度も目撃している対応方法は、自分の中にバリエーションとして蓄えられていきます。そしてあるときに「あ、こうしてみよう」と対応の選択肢に上がってくるようになるのです。
もちろん最初の一回はスムーズではないでしょう。定着して、当たり前にできるまでには繰り返しが求められます。
ですが、見たことのない対応は、選択肢として上がってくることさえありません。
効果的な技術を見たことがあって、どんなものかを知ってさえいれば、まずは「使おうとする」ことができます。
ここが劇的な違いを生み出すポイントです。
今までのパターンとは別のことをするのですから、それだけで別の結果が得られやすくなります。
「見る」ことが重要な理由には、どんな流れでコミュニケーションが進んでいくかをイメージできるところもあります。
どういう方向に進んでいくのが望ましいのか?というゴールが想定できます。スムーズな人間関係では、コミュニケーションの展開も、落とし所も、当たり前のように想定できているものでしょう。
ところがトラブルになるコミュニケーションでは真逆です。相手のメッセージに反論したり言い返したり、その場をしのぐための応答が繰り返されがちです。
望ましい方向性が想定されていないままコミュニケーションをする。言い換えると「どうしたらいいか分からない」から、とりあえずで対応するしかないのです。
どんな形にコミュニケーションが着地すればいいのか?
どんな流れで着地点まで進んでいけばいいのか?
そこを想定できていることが、人間関係をスムーズにするコツです。
厄介な人間関係が続いているとしたら、その場をスムーズに進める『効果的な対応』を見たことがないのが最大の原因かもしれません。
本トレーニングプログラムでは、技術を使いこなせるようになるための実習機会ももちろん大切にしていますが、それ以上に重視しているのが「知ってもらう」ことなのです。
人間関係の効果的なやり方を「見たことがない」、「知らない」というだけの理由で、悩み続けていたり、諦めてしまったりするのは残念なことだと思います。
少なくとも私自身のターニングポイントは、
「こういう人がいるんだ!」
「こんな対応方法があるのか!」
と知るところにありました。
その後でどこまで技術を求めるのか、どこまでの成果を望むのかは人それぞれでしょう。
ですからトレーニングプログラムとしても、できるだけ自分のペースで無理なく学べるスタイルにしたいと考えました。
動画と練習を繰り返していただくほど、効果は上がっていくものと期待しています。
目下のトラブルに最優先で取り組むために、該当する技術を集中して学ぶのもいいでしょう。
ゆっくりと少しずつ理解を深めていくのもいいでしょう。
まずは「知る」ことから始めていただきたいと願っています。知らないだけで続いている不幸の連鎖が、小さな一歩で止まるかもしれません。
- 1日本文化ならではの『寄り添いの言葉がけ』
《応用ケース:相談、愚痴、クレーム対応、教育、家族関係 etc.》
- 2記憶に残る聞き役になれる『ペーシング質問法』
《応用ケース:社交、営業、接客、インタビュー、友人関係、家族関係 etc.》
- 3相手の世界を理解する『ビリーフ・リスニング』
《応用ケース:相談、面接、営業、クレーム対応、部下・生徒指導 etc.》
- 4人間関係を無難にこなす『嫌われない会話術』
《応用ケース:社交、雑談、営業、接客、友人関係、職場関係 etc.》
- 5相手のニーズを把握する『メタモデルの応用質問法』
《応用ケース:相談、営業、接客、教育、面接 etc.》
- 6場をコントロールする『ファシリテーション返答法』
《応用ケース:会議、雑談、友人関係、社交、職場関係、生徒指導 etc.》
- 7感情への感度を高める『非言語メッセージの観察法』
《応用ケース:相談、教育、指導、家族・友人関係、営業、接客、雑談、クレーム対応 etc.》
- 8主観・共感・客観を使い分ける『聴き方の知覚位置』
《応用ケース:相談、雑談、学習、教育・指導、家族・友人関係、クレーム対応 etc.》
- 9自分を分かってもらうための『本心の言語化法』
《応用ケース:話し合い、依頼、教育・指導、家族・友人関係、自己PR、営業 etc.》
- 10感情に振り回されなくなる『期待の手放し方』
《応用ケース:話し合い、家族関係、職場関係、友人関係、教育・指導、相談、クレーム対応 etc.》
- 11NLP的『心を読み解く技術』
《応用ケース:家族関係、会議・話し合い、相談、クレーム対応、面接、営業 etc.》
- 12『対立を協力に導くコミュニケーション』
《応用ケース:家族関係、友人関係、クレーム対応、交渉、話し合い、教育・指導 etc.》
セミナー形式
これら12の技術を達人レベルまで身につけるには、ある程度のトレーニング期間が必要になってしまうのは想像どおりです。
「でも、まとまった時間がとれなくて…」
「何度も週末にセミナーに通うのは大変で…」
といった方もいることでしょう。
そこで本トレーニングプログラムでは、「自在に技術を使いこなせる」まで習得することよりも、
- 世間に知られていない人間関係の達人のやり方を『知る』
- 技術として身につけるための『コツを掴む』
のほうに重きを置きました。
実際には、達人レベルにまで技術を身につける必要がある人は少ないものです。厄介なケースでも、対応の方針が分からないことが悩みの種になっていることもありますから。
繰り返しになってしまいますが、何よりも重要なのは、効果的な対応を「具体的なコミュニケーションの流れ」として1.『知る』ことです。
「実際にどんな言葉のやりとりが起きるとスムーズに進むのか?」
「どんな気持ちの変化が起きて、望ましい落とし所に辿り着くのか?」
これを具体例で数多く見て『知って』いるほど、あなた自身の中にも自然と方針が見えてくるようになります。
そして多くの人が達人を見逃していることから分かるように、その望ましい「具体的なコミュニケーションの流れ」をポイントとして整理する必要があります。
具体的な事例を見ながら
「あ、今、ここのステップだ」
「ここで次のステップに移った」
のようにポイントに落とし込んで、2.技術の『コツ』を把握していきます。
それからポイントを頭の片隅に置きつつ、今度は自分目線で「技術を使っているところ」を体験します。
ここが練習にあたります。
もちろん『コツ』はNLPの観点で解説されます。
いわば「達人の頭の中を、自分の頭の中に再現する」ようにして体験学習するということです。
こうした学習プロセスを効率的にして、しかも多くの人が気軽に近づけるようにしてくれるのが、
『動画とオンラインセミナーの組み合わせ』です。
忙しい方でも無理なく学べるように、
さらには急激な詰め込みにならないように、
そして達人を目指したい方が十分な練習期間を取れるように、
12の技術を毎月1つずつ扱っていきます。
具体的なトレーニングプログラムは、次のような流れで進みます。
構成
- 月一回の解説動画の配信(全12回)
- 月一回のオンラインセミナー(全12回)
- オンラインセミナーの動画アーカイブ
進行
- 好きなときに講義動画で内容理解
- 2時間半のライブトレーニング
- 欠席の場合は動画アーカイブで
- アーカイブで復習もOK(デモの分析はオススメ!)
- ライブトレーニングは何度でも参加可能(次期に)
内容の特徴
- 各回は独立した内容(場面ごとの技術)なので目標に合わせてトレーニング可能
- 同じ原理が繰り返し登場するので自然に身につく
- その日からすぐに実践できる実用的なやり方
一度の学びで身につくか不安です。
何度でも無料でご参加いただけます。
NLP2.0は、繰り返し受講が無料です。
つまり、来年以降も無料でご参加いただけるということ。
トレーニングを繰り返すたびに上達します。
どうぞ達人の技術を満足いくレベルまで習得ください。
オンラインセミナーに参加したことがないのですが…。
インターネットができる環境が必要です。
機器とインターネットができる環境であれば、人気のセミナーを、ご自宅に居ながらにして受講いただけます。
「Zoom」のインストールはじめ、操作が初めての方、まだ慣れていない方も、操作はとてもシンプルですのでご安心ください。
NLP資格を持っていないのですが…。
義務教育を修了した方であれば、どなたでもご参加いただけます。
NLPの観点で整理されていますので、NLPの経験があるほど習得がスムーズな面はあるかもしれません。
ですがNLPを学ぶセミナーではありませんので、NLPを学んだことのない方でも無理なくご参加いただけます。
実際これまでにも、NLPを学んだことのない方のご参加はありましたが、まったく問題ありませんでした。
どうぞご安心ください。
日程が合わない回があります。
ビデオ受講で繰り返し学習できます。
各回とも、後日、無料でセミナーの動画をお渡しします。
- 「急な都合で参加できない」
- 「4日目は参加できない…」
という場合も安心です。
また、セミナー動画のほかに、講義動画も繰り返し視聴できます。
セミナーに出席した場合でも、動画で復習することは可能でしょうか?
参加した回も、もちろんビデオ受講できます。
Clear NLP Japanでは、受講者全員にセミナーの動画をお渡ししております。
後日、動画を見ることで、
- 繰り返し復習することができる
- 講座中に、ノートを取ることに気を取られずに、講師の話に集中できる
- 時間が経ってから見返すことで、新たな気づきを得る
などの効果が得られます。
どうぞ有効にご活用ください。
どのような方がアシスタントですか?
NLPトレーナーやプロ講師が務めます。
真剣な学びをサポートするには、アシスタントのあり方も大切です。
Clear NLP Japanでは、他団体のように過去の受講生が学び直しも兼ねてアシスタントを務めるのとは違い、NLPトレーナー資格取得者、又は関係団体の日本実践カウンセラー協会講師がアシスタントを務めます。
専門的技能と知識、そして経験を積んだ人間がアシスタントを務めるからこそ、あなたのNLPの学びを徹底的にサポートできるのです。
支払いはどのようにするのですか?
銀行振込/クレジットカードからお選びください。
お申込み後1週間以内に、銀行振込またはクレジットカードでお支払いください。

分割払いは可能ですか?
割高とはなりますが、分割払いもできます。
若干割高とはなりますが、5回払い(手数料5%)、10回払い(手数料7%)にも対応しております。
分割払いをご希望の場合は、お申し込みフォームの通信欄に、「分割払い希望(5回)」or「分割払い希望(10回)」とご記入ください。
- 分割払いは、クレジットカードのみの取り扱いとなります。
開催日程

第2期
【オンライン】
’25年9月~’26年8月
| 原田 幸治トレーナー |
|---|
① 2025年 9月 11日(木)
② 2025年10月 9日(木)
③ 2025年11月 13日(木)
④ 2025年12月 11日(木)
⑤ 2026年 1月 8日(木)
⑥ 2026年 2月 12日(木)
⑦ 2026年 3月 12日(木)
⑧ 2026年 4月 9日(木)
⑨ 2026年 5月 14日(木)
⑩ 2026年 6月 11日(木)
⑪ 2026年 7月 9日(木)
⑫ 2026年 8月 13日(木)
- 毎月第4木曜日(19:30~21:30)
- 30分程度の延長の可能性があります
開催要項
| セミナー名称 | NLP2.0 |
| 開催場所 | 【オンライン】 詳細は、お申し込み後「受付メール」でご確認いただけます。 |
| 参加費用 | 217,800円(税込) |
| お申込み方法 | お申し込みフォーム |
| 申込締切日 | セミナー開始の10日前 |
| お支払方法 | 銀行振込/クレジット
|
| トレーナー | 原田幸治 |
| 受講対象 |
|
| 特典 | ① 受講後の実践オンライントレーニング・オブザーバー参加費永年無料! このプログラムは翌日から使えるものではありますが、全てを使いこなすには充分なトレーニングを必要とします。 |
| ② 実践リアルワークショップにご招待!(日程未定) オンラインでは出来ない、リアルな場での実践トレーニングにご招待します。 | |
| ③ 《NLPオンラインフォローアップ研修》に無料ご招待! このプログラムのベースになっているのは、言うまでもなくNLPです。 そこで、NLPの全体像を理解するためのワークショップに無料でご招待します。 《日程》 ① 2026/05/21(木) 毎回第3木曜日(10:00~12:00) | |
| 備考 |
|