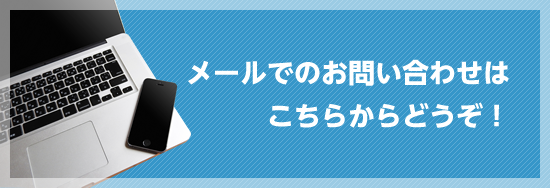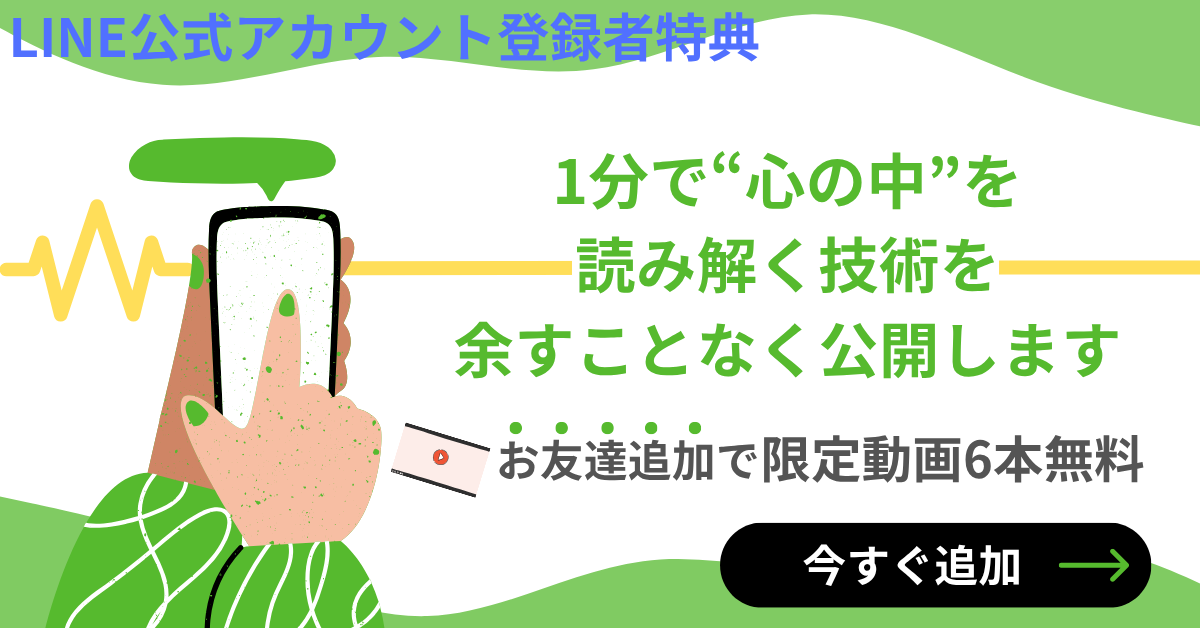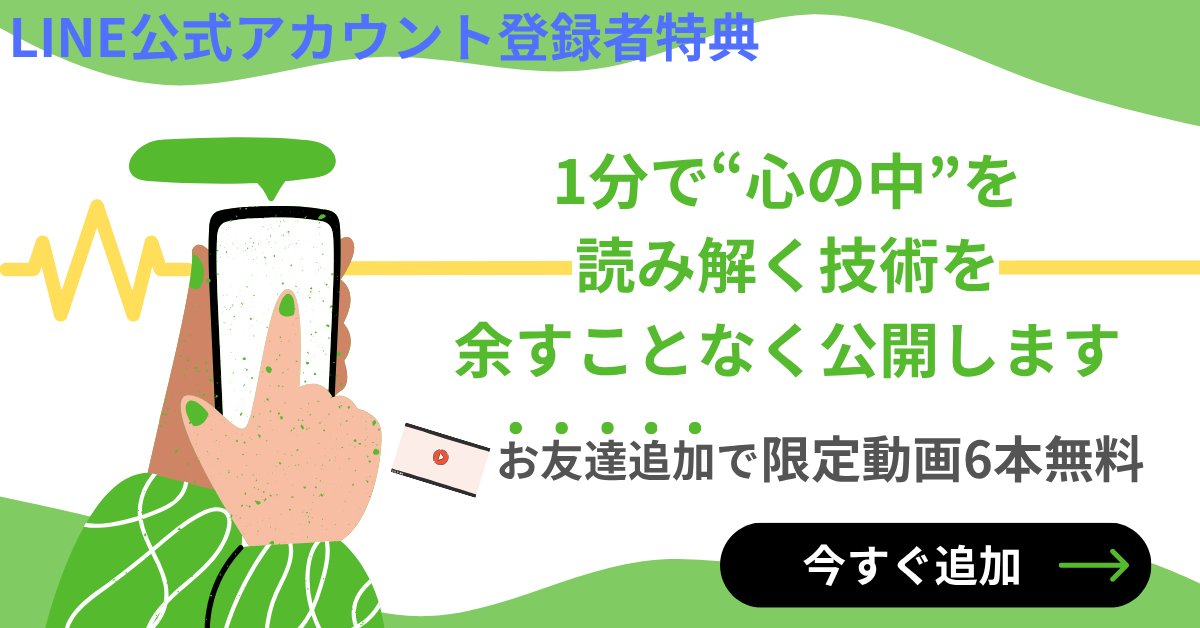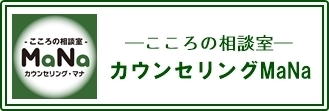リフレーミング
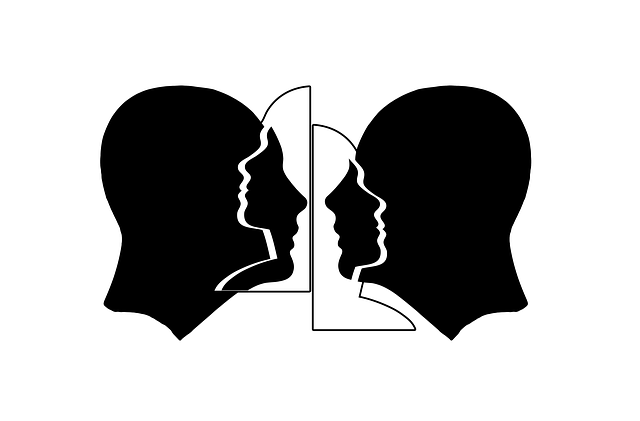
物事の捉え方が変わること、変えること。
捉え方の“枠組み”を『フレーム』としたとき、そのフレームを新たなものにする作業が『リフレーミング』。
“捉え方”には様々なものがあるが、NLPで一般的なのは「体験内容の意味づけ」という捉え方をリフレーミングするケース。
「これは〇〇だ」という認識に「良い/悪い」のニュアンスを加えて評価・判断するのが意味づけ。
この意味づけを自由に変えられるようにするのがリフレーミングということ。
必ずしもポジティブに意味づけするわけではない。
【NLPにおけるリフレーミングの分類】
◇ 意味のリフレーミング
体験内容の意味づけを変えるもの。
主に「問題」と判断される意味づけを変えて、問題ではない状態にする。
『状況のリフレーミング』と『内容のリフレーミング』に大別される。
◇ 6ステップ・リフレーミング
「問題」を解決するための対応を考えるときの「これはどのような問題か?」という捉え方を変える意味でのリフレーミング。
“問題”という認識はそのままに、解決策を探す方向性を変えるもの。
いわば“問題の種類”のリフレーミング。
いくつもあり得る“問題の種類”の捉え方のうち、6ステップ・リフレーミングでは「肯定的意図を満たす手段が現状に合っていないのが問題」とリフレーミングして、代替手段を見つける作業を行う。
【リフレーミングの技法】
◇ 意味のリフレーミング meaning reframing
意味のリフレーミングが可能になるのは、そもそも人が物事の一側面だけに注目して意味づけしているから。
その注目の仕方を「フレーム」としたとき、別のフレームに置き換えるためには、それまで見過ごしていた側面に注目する必要が出てくる。
そのための見過ごしていた注目ポイントの探し方として『状況』と『内容』に区別するのが効果的。
- A.状況のリフレーミング contexet reframing
「同じ物事が別の状況におかれたら、別の意味を持つ」可能性を考える。
一般的に分かりやすいリフレーミングのターゲットは、人の振る舞いのパターン(行動や考え方など、個性にあたるもの)。
ある状況では問題視される個性が、別の状況では役に立つという発想。
【技術の例】
「大勢がいる場だと思ったことが言えないんです」
→「そのように慎重に様子を見て対応しようとする持ち味が、大事な意思決定のときに役立ってきたかもしれませんね」
- B.内容のリフレーミング content refaming
「1つの体験内容そのものについて別の意味に解釈する」可能性を考える。
状況も、体験内容も同じ。
ただし内容として見過ごしていた情報を追加して、注目するポイントを変える。
典型的には、“残念な出来事”や“苦手な物・人”がリフレーミングのターゲット。
同じ出来事でも人によって受け取る印象が異なることを踏まえれば『内容のリフレーミング』の可能性はいくらでもある。
【技術の例】
「今日の社内プレゼンのとき、部長がずっと険しい顔をしていたんです。よほど私の提案がマズかったんでしょうね…、あぁ。」
→「あれ、私は今日、部長は体調が悪いのかと思って見ていましたよ。時折、アゴを触っていましたから、もしかした歯でも痛いのかなぁって。それに部長の癖ですけど、あの人、納得いかないときは目を背けるんですよね。あなたのプレゼンのときは真っ直ぐ見ていたと記憶していますが…。」